もはや人類の義務教育である「桜井政博のゲーム作るには」、もちろんゲーマーの皆さんなら見てますよね?
んで、本記事はその「ゲーム作るには」を見ながら考えたことをうだうだと喋る記事です。
別に「桜井さんの上げていた要素を深掘する!」と言うようなおおげさなことを言いたいわけではなく、主に「雑の談」です。
が、自他ともに認める?厄介逆張り老害お客様ゆとりゲーマーなので、「ゲームについてこんなことを思うってる変な人がいるんだなぁ」という面白さはあるかもしれませんし、僕がそう思っているだけで実は一般的な思考であり「あるある」と読めるかも知れません。

それを判断できるのはそこのあなただけ! というわけで読んでみてネ ☆ミ
マンガアプリなどでよくある、マンガを読んだあとに眺めるコメント欄程度にダラダラと眺めていただければ幸いです。
元動画はA~KまでのアルファベットでカテゴリわけされててAから順に……
「仕事の姿勢、ゲーム性、企画・ゲーム設計、仕様、チーム運営、グラフィック、モーション、エフェクト、サウンド、UI、プログラム・テクニカル、雑談、企画コンセプト」
……となっているので、それに則って見出しを分けています。
記載のない動画もまだありますが、ゆくゆくは全動画に触れていきたいなぁ。
仕事の姿勢カテゴリの動画(A)
とにかくやれ!!【仕事の姿勢】

タイトル見た瞬間「Just do it おじさん」が脳裏に浮かんだw
これ、普遍的な人間の悩みだよなぁ。
ただワイくらい怠惰になると「部屋が爆発するならこれ以上頑張らなくていいじゃ~ん!」ってなるのでダメです(ダメ人間)
結局やらないときはやらないんですが、マリオカートの「3・2・1・GO!」を頭の中で思い浮かべつつポモドーロタイマー※をスタートすると、スタートダッシュを切りやすいような気がします。
※ポモドーロテクニックと言って、25分作業、5分休憩を繰り返し、4セット後30分休憩してまた4セット25分作業、5分休憩して……とすると集中して作業ができるというライフハックです。
悪い意味での効率厨こそハマりやすいワナなので、ほんと、「とにかくやれ!」はなんどでも見直したいね。
ゲーム性カテゴリの動画(B)
落ちものパズルのゲーム性 【ゲーム性】

わりと「んー?」と思うところの多かった回。
テトリミノを回転させまくるという攻略はゲーム性の観点で言うならむしろぼやける気がするんだよなぁ。「リスクを引き付ける」と言ってるけど、「リスクを引き付ける=リターンに近づく」はそもそもテトリミノが上から下に落ちてくることを指すのが一般的に思うんだよなぁ。落下直前の時間稼ぎはリスクリターンとはまた別軸の要素だと思う。
ちなみにゲームデザインとしてもイマイチ美しくない仕組みだと思っていて回転させてペナルティを確定させず相手のミス待ち、みたいな戦略につながるかもしれないけど、それ美しくなくない?
「どこに置くか考える時間を稼ぐテクニック」としてなら理解できるけどそれは「損失を抑える」ことであって「能動的にリターンを得る」とはまた別な話な気がする。
さてテトリスに絡めたゲーム性の話をまた続けます。
「積み上がっていくブロック」をリスクと定義するならば、ほぼイコールで「現実の経過時間」がリスクということなんですよね。多くのアクション要素のあるゲームもそうで「時間経過=リスクの肥大化」なんですよ。
で、そこから個人的にいつも思うことなんですが、ドラクエを筆頭とした多くのJRPGをなぜ個人的に好きになれないかってことが言語化できてきます。JRPGってこの動画でいう「ジグソーパズル」なんですよ。最近個人的に頭の中で良くつかう言葉があるんですが「無限リソースゲー」なんですよね。「時間さえかければ誰でも無限に答え(≒ゲームクリア≒レベル上げ≒経験値の積み上げ)に近づける」というゲーム。
もう少し踏み込むなら(定義がちょっとガバるかもしれませんが)「(広義の)時間制限」が僕の思うゲーム性の大きな要素の一つなんですよね。
動画に話を戻すなら、ペントミノ含めてですがもチェスタイマー(各々の持ち時間)があれば多くのアナログゲームに勝手にゲーム性が高まる雰囲気はありますし、それこそJRPGなんかも制限時間をつけることで有限リソースになり、リソース管理というゲーム性が生まれるんですよね。
……そういう意味で言うと、ドラクエはもしかしたら「ドラクエ」というジャンルのゲームで「RPGの皮を被った誰でもクリアできる演出装置」として作られていた説は濃厚ですねぇ。
それと最後、5分で思いつくのがすごい……のはそうなんだけど、「5分で思いつけるようになろう」。「すごいものではないと思うところまで視座をあげよう」ってのが本質だと思うんですよね。んで其のために桜井さんが百万回言ってる通り「なぜそうなっているのか?」を突き詰めるってのが大事ってことで。
だいたい「なぜそうなってるか」を掘り続けたら、正解の付近に着陸できるんですよね。ホームランとまでは言わなくてもバットにかする程度のレベルには必ず到達できる。
……と今言語化して思いましたが、僕がこう文字を生産する理由の一つは、「なぜ? あるいはこうだろう。」の積み重ねの先にあるかもしれないホームラン(納得)の幻想を追ってるからなんだなぁと腑に落ちた気がします。
対戦は複雑になるもの? 【ゲーム性】


空手道、初めて見たけど普通に格ゲーしててすごいわ。というか今思うと”格闘”ゲームなんだから、格闘技における駆け引きを再現したらそれがゲーム性になるよなぁ。
まぁ、もちろん、その上で「『ゲーム性』以外」の部分をどう出すか。どういうゲーム性を足し引きするかというのこそがこのジャンルで語られる部分であるとは思いますが。
どうでもいいけど桜井さんのパンチ、無駄な動きがなくてすき。
「さほどの駆け引きを産まないのに複雑なルールがある」ってのは(そんなにプレイするわけではないけど)ボードゲームで結構感じることが多い。「こんだけ説明長いのに、やってることババ抜きでは?」みたいな感じで。
まぁでもゲーム性を「駆け引き」とするなら、対面での心理的駆け引きもゲーム性になり、ババ抜きも最後「2分の1の運ゲーではない」と言えるのかもしれないけども……個人的には、うーんですけどね。
マリオのジャンプはかなり意外。着地順DX,SP,WiiU,X,初代なんだね。Xが一番遅くて初代は三番目くらいかなぁ、と思ってた。
「当たり前を当たり前に思わない」ってめちゃくちゃ大事な言葉だよなぁ。なんとなく付けてただ不快感を増す要素になってること、死ぬほどあるよなぁ……。
ごほうび要素はまっ先に 【ゲーム性】

「ご褒美」がゲームを進めるのに有利になる要素だと、それは欲求ではなくて義務になってしまう
これ、昔DOOMEternalの感想をさらっと書いたときにも考えてたんですが……
(FPS(DOOM)におけるチャレンジ要素での作業感の強いパワーアップについて)
「パワーアップアイテムを使わない」とかそういうチャレンジなら、僕のプレイスタイルでいうなら苦しみつつも無限にデーモンに挑み続ける楽しさを感じられると思います。
(パワーアップアイテムになると)上手い人がより強くなる構成というか。
だからこそそこにキャラクタースキンとかのアンロックを置けばいいんじゃないでしょうか。集めたい人は集めてねスタイル。
(パワーアップアイテム=ご褒美が)難度に関わってくると、集めないのが許されない感じになってしんどいんですよね。
って話ですね。(若干修正やわかりやすいよう改変しています)
「ご褒美」がゲームを有利にする要素だと、「ご褒美」を得られないほどに下手な人がより苦しみ、「ご褒美を得よう」と思う程度にゲームなれしているプレイヤーには義務感が生まれてしまう、というジレンマ。
むしろだからこそ「ご褒美(アイテム)」を得るために躍起になるというプレイ動機にはつながると思いますが、それって割とすぐ苦しみになる動機だと思うんですよねぇ。義務になる。
言い方を変えると、本質的でブレない喜びはやはり「勝利」だと思うんですよね。
「『勝利』というご褒美だけでは今のゲームとして弱い」みたいな発言ありましたが、今を持って最も強い要素だと思います。
ただそこにたどり着くまでのハードルが高いと遊ばれない。結果的にカジュアルに得られるジェネリック勝利として「アイテム」とかがある。
でもそうなるとカジュアルなってしまったがゆえに「勝利」という果実の甘みを真に味わうことができない。そんな感じ。
とは言え別に「ご褒美」を否定するわけではないです。むしろ肯定。ゲームにかぎらず人生とは「ご褒美」をいかに得るかというものじゃないでしょうか。
でも、だから、そことイコールで「ご褒美を上げれば良くなる」ではない。
とはいえ、ご褒美を集めるゲームは好きです。「アイテムを集めることに振り切った」ことが条件ですが。
中途半端にゲームを阻害する要素として入れてると桜井さんが言うような「ちょっと嫌になることもある」ってのは、非常によくあるかと。
だからこそ「大事」だけど「雑に入れて良くなるもの」ではないと思います。
そして余談になりますがゲームを有利にするためではなく「ゲームそのもの(キャラクター、BGM、ストーリー、そして総合的な勝利)が「ご褒美」になっているからこそ僕は東方Projectにここまで心酔してるんだなぁなどと思いました。
そしておそらく僕が一番好きなゲームであるFTLも「勝利の果実」の美味さが段違いだから、一番好きなゲームでもあると思いました。
まぁこれは本当にプレイヤーの勝手な言い草ですが、結局そういう「ゲームをプレイして得られる勝利や快感という最高のご褒美」を提供出来ないゲームの小手先だなぁ、と思ったりします。もちろんそれを含んだゲームであるFallout3とかもめっちゃくちゃ好きですが、仮に好きなゲームランキングを作ったとしたら、真っ先に上げる感じではないですね。いや、Fallout3は本当に好きなんだけどさ。
あ、あと、ふと思ったのが、小さな勝利とその気持ちよさを増すってのは効果的だよなぁ、と思う。Borderlands1とか今回の本題含めてだけどメチャクチャいい例だと思っていて、まさに行動のすべてが報酬につながる素晴らしい仕組みなんだよね。
これはアイテム的な報酬はもちろんなんだけどその上で、「敵を倒す」という行為の気持ちよさが強い。大げさなくらい頭がはじけたり体がバラバラになったりするので、破壊のリアクションがとにかく気持ちいい。ここらへんも変にリアルにするより、嘘でもいいからより気持ちよくなれるようにみたいな調整ありがたい限り。で、かつそれがプレイ継続の報酬になっている。「撃つ音が気持ちいい」から、ついつい次の敵、次の敵、と倒していく欲求になり個人的には十分報酬になっています。
で、それを延々繰り返すゲームだから、延々気持ちいいんですよね。無限に報酬系を刺激する。
「ご褒美」によるゲームバランスの調整が含まれると色々問題が出てくるから、「ゲームバランスに関わらない部分のご褒美」こそチカラを入れてほしいなぁというゲームへの願いがありますね。いちプレイヤーとして。
はてして敵は必要なのか【ゲーム性】

赤ずきん茶番、草
「ゲームの面白さの一つはストレスと解放である」と常々思っているので、この話は非常に面白く見てました。ちょっと前の「浮遊感は落ちてこそ生まれる」とかもそうですが、描きたい要素があるならその反対の要素をしっかり描くことこそ重要なんですよね。
当たり前のようになっていることは理由があるからそうなっています。
しかし疑問を持つことは良いことかと思いますので掘り下げてみます。
ってめちゃくちゃいい言葉だよなぁ。
ところでコメントを読んでいるとMOONの話が出てきたりするけど、本質的にこの動画での「敵」は「障害(ジャマモノ)、ストレス」のことだと言っているのに、なんでMOONとかでてくるのかよくわかんないんですよね。
「設定」として「ただ敵を倒すRPGのアンチテーゼ」を描いていて結果的に「標準的なRPGにおける戦闘シーンが存在しない」だけで、ゲームプレイにおける敵(=障害=ストレス)はゲーム内に山のようにありますからね。
「人間は文章を読んでいるのではなく、文章中の脳内で関連付けるワードを拾って脳内で組み合わせているできの悪いAIのよう」みたいなのどっかで読んだ記憶があります(し、僕も大概なのです)が、それは動画でも同じなんだなぁ。
まぁ、人類にそもそも敵が必要だと言うのは、あらゆるところで目にしているので……。ね!
企画・ゲーム設計カテゴリの動画(C)
自然なチュートリアル 【企画・ゲーム設計】

キーコンでチュートリアルボタン変更の必要があるのは、開発者目線で目から鱗。
↑に関連する要素で言うなら、諦めて「(初期設定のボタンではAボタンです)」みたいに書いてるゲームはたまに見かける。
「自然なチュートリアル」ってそれこそマリオブラザーズやドラクエ1という優れた良い例があるし、複雑化しているゲームでも本質は変わらないわけだからサクッと作れそうなもんだけどねぇ。
んでもまぁこうやって言っている桜井さんの作品(スマブラ)ですら最初放置でムービーによる操作説明という不親切仕様な気もするから、難しいのかなぁ。
クソほどゲームが生まれて未だにクソチュートリアルを大量に目にするから実は最も難しい部分のほとつなのかも。
いや、でも、「Aボタンをおせばジャンプ! Bボタンで攻撃!」みたいなことを喋ってるチュートリアルは全部クソだと思います。押せばわかるだろ。「演出的に興味深く面白いチュートリアル」というのもある(例えばチュートリアルではなく「戦闘訓練」という体裁でチュートリアルを触らせるだとか)けど、結局それも気分を乗せるかどうかでクソなのには変わらないからねぇ。
個人的には「面白くなってないのに複雑化(要素の増加)させることを『面白い』につながる」と思ってる開発者が多いのが元凶な気もしますが……結局ややこしいチュートリアルを作るのはややこしいシステムがあるからで、シンプルに面白いゲームかやられた時に反省(自省)を促せるゲームを作ればいいだけでは? という気持ちしかない。
んんんんんんん、でもそれもあんまりユーザーに寄り添った考え方でもないんかなぁ。案外みんな手取り足取り教えてもらいつつややこしい装飾の多いゲームが好きだったりするんか?
というのも含めてだけど、「得られるスキルのお試しは製作コストがかかる」みたいに桜井さんも言ってるけど、普通に「スキルの振り直しが簡単」っていうシステムじゃだめなんか?
ここらへん本当に世間のゲームに対する捉え方と僕の捉え方が違いすぎてるように感じるところなんだけど、「まず触れる」がすべての基本だと思うんだよなぁ。
それで理解出来ない人や詳しくしりたい人のために後付けチュートリアル(ゲーム内辞典てきな)や「デメリットの無いスキルの振り直し」をプレイヤーに選ばせるってのがベストだと思うんだけどなぁ。逆にそうしない意味がよくわかんないレベル。
そういう意味で「自然なチュートリアル」とはいえないけど、スマブラ形式のチュートリアルは個人的な好みに合致はしてる。
んだけど、そもそも格ゲーのチュートリアルってどこまでがチュートリアルとするかは非常に難しいところだとも思う。
このチュートリアル関連は話せば話すほど無限に掘れるところだと思うからこれ以上は一旦語るのやめるけど、たぶん桜井さんの動画の方でもまた追加でなんか出てきそうだね。
フレームを計れるようになれ! 【企画・ゲーム設計】

言われてみると、たしかに15,30,60フレあたりは普通にできるなぁ
動画を見る前、タイトルを見た時は「いやそれはいつもの桜井さんの特殊技能でしょw」と思ってました。
頭わるわるなので「1フレが0.016秒であること」を知識として知っていましたが、30フレームが2分の1秒である、みたいな考え方が出来てなかったんですよね(あほあほ)。
逆に言うと30フレが2分の1秒であるならば、120BPM(Beats per second……1秒間に何泊刻むか)における「拍」が「30フレ」を刻めてるんだなぁなどと慧眼。
そしてゲームの動作単位が1フレで0.016秒なのになんでゲーム内タイマーが存在するゲームでは正確に時間を計れるんだ? という疑問もあったんですが(TAとかやってるとぶつかりがちな悩み)、それにも回答をもらえて色々スッキリした。なるほど、次のフレームでどの程度「はみ出ているか」で計測ができるんだなぁ。
ちなみにですが、「1秒(60フレ)」を体に染み込ませるために役立ったのは僕はこの動画です。
「TOHO CLOCK」という大勢の東方二次創作者が集まって作る二次創作合同企画なんですが、タイトル通り「時計」の「ピッ」という1秒(60bps)毎に刻まれる音に合わせて動画と音楽が展開されるんですよね。
なので、この動画の「ピッ、ピッ」のリズムを中間を取りながら楽しげなアレンジと動画とともに楽しめば、30fpsと60fpsはモノにできます。
あと、昔ドラム叩きてぇ~! って思ってた時に正確なリズムが大事ってどっかで読んで、メトロノームアプリとかでリズム感を刻んでいたのも影響してるかもしれません。それによって三連付(fpsで言うなら20,20,20)とかもなんとなくわかるようになってました。
どんどんゲームと関係なくなりますが、僕サウナが好きなんですけど、サウナでもこの技能役に立つんですよね。何分計かわからない砂時計がある時、大体体感で測れるようになってると便利なんだよね。
こないだもひっくり返して目をつぶりつつ5分をカウントしたあとに,目を開けて約4秒後に砂が流れ落ちたので「あぁ、これは5分計だな」ってわかったことがありました。ある程度慣れれば、誤差1%程度で5分くらいなら体内カウントできるということです。
つまり何が言いたいかというと先天的な特殊技能ではなく、後天的に習得可能な技術です。フレームを計るというのは。
仕様カテゴリの動画(D)
速度の単位 【仕様】

プレイヤーはあまり意識することのない分野の話かと思うけど、それでも「あぁ、そういえばそういうことか」みたいな気付きはあるよね
スーパーマリオブラザーズデラックスをプレイしたとき、妙に早く見えたけど、そりゃ画面の解像度が低いなかにファミコンと同じものを詰めようとしたらそうなるよなぁ。
ところで「スプライトベース」という単語、耳馴染みがなかったけど他の動画で説明されてたかな? 3DCGとかじゃなくて、背景画像の上で要素を動かすようなものをスプライトというっぽいけども。
リアルの単位で設定されると、こんど「環境によるリアル単位の違い(不慣れさ)」が出てきますよね。ヤード・ポンド法的な話です。ちなみにマジで関係なくなりますが、小学生くらいのとき社会かなんかの教科書を読んでいたら「キュビット」という単位(指先からひじまでの距離)みたいなやつが出てきて「ガバガバすぎるだろ……」と衝撃を受けたことを思い出しました。どうでもいいですね。
遅さは罪 【仕様】

わかりみしかなかった
私のゲーム制作においてはゲームを操作している時間、実時間というのを意識しています
中略
なんにも遊ばせていない楽しませていない時間は本当申し訳ないと思っているぐらいです

それよ!!!!!!
僕も多分一番ゲームにおいてキレてるところな気がします。
エルデンリングのクソ仕様を殴る記事を以前書いたんですが……
ちなみにたまに「SSDならロードが5秒で~」みたいなレビューもあったりしますが、そもそも5秒ですら長い上に「やられたと判断した瞬間からリトライしたい場所」までが「実質ロード時間」なんですよ。
という内容。これ、ようするにこの桜井さんの動画で言う「実時間」を、「非実時間」目線で書いたことなんですよね。
あとロード時間を0にするのは「技術的に不可能」というのも理解できますが、正直「技術的に不可能」の上にあぐら書いてるゲーム多いとも思ってます。
これも以前「2022年にプレイした神仕様」について語ったことがあるんですが、「すべてのゲーム、無限回生で良くない?」という思いしかありません。特にリトライにロードを挟むゲーム。それこそスーパーミートボーイレベルのリトライ時間が可能であればそれがベストかとは思います。
ちなみに桜井さんは「ムービーは箸休めとしてあってもいい」と言ってて例としてダクソを出してますが、ダクソの仕様も個人的にはダメで、「リトライの手間を増やす」のがクソなんですよね。
「ムービースキップできる」とはつまり「ムービースキップしなければならない」ってことで、リトライの手間が増えるんですよ。(もちろん「じゃあムービースキップできなければいいんだな!」という意味ではないですよ)
それこそアノロンに入るときのように、「リトライが絡まず、1度しか流れないムービー」はあってもいいと思いますが
んで、ムービーを見逃した人はどうするんだっていう話もありますが「ムービー閲覧機能の実装」が解決策第一位、「セーブを分ける」のが第二位です。
話がそれました。
ゲームを作る方には、「プレイ可能な時間が長いゲーム」を是非作って欲しいなぁ、と願うばかりですね。
それと余談ですが、新パルテナですら僕は「ゲームプレイ開始」までの時間がなげぇな、と思っていました。まず名前と誕生日の入力とかいらないですし、チュートリアルもいらないです。どれも「プレイしてから決める(学ぶ)」で良くないですか?
その点完璧なゲームは「不思議の城のヘレン」と「らんだむダンジョン」です。共通点として「ニューゲーム」を押した直後にフィールドに放り投げられて移動できるようになります。
チーム運営カテゴリの動画(E)
10人チームは7人分 【チーム運営】
・桜井さんはこの「出来ない量」まで織り込み済みだから、過不足無くゲームという結果を生産できるのかね。それにしても7割の出力は効率が良いのでは?
・「良さ」を形にするために結果手を動かしているだけで、「良さ」を思考、想像できるかというのが最も重要なんですよね。昨今のAI云々というのも「手」としての性能が上がっただけ。
・逆説的にZUNさんなんかは伝達のロス無く100%がゲームになってるから、その世界がツボに入れば100%信者になれる。もちろん開発規模の問題で表現したいコトを削るような妥協はあるだろうけどそこも伝達時のロスではなく「削る」という意思を持って削る部分だから意味合いが違う。
・そもそも会話ややり取りにおける情報伝達時の損失は必ずあるからなぁ。結局、本当にできる人が1人ですべてを作る作品が最高の作品ではという気持ちがある。消費者としては。
・その上で仕方がない部分としてチームでやる時の情報伝達量を増やす特訓としてプレゼン会をやろう、というような仕組みづくりが優れている。そりゃ良いもの作るようなぁという感じ。
・「人月」という単位を昔聞いた時「そうは(1人で1ヶ月の作業が10人なら10人月!)ならんやろ」みたいに思ったことを思い出した。
グラフィックカテゴリの動画(F)
レタッチ監修(グラフィック)
・個人的に「別に全部どうでもよくない?」くらいのところなのに着目できる能力。結局「正解」があって、それを出力する手足としてスタッフを動かせている「脳」になれてることが特異なんだよなぁ
・黒を濃くして白を上げず目立たせるという手法、マジでありがたい。「よく見える」ことを重視して、「画面から目をそらせない」ゲームであることを忘れてるエフェクト、結構あると思うわ。まぁ、オプションで明るさ調整みたいなのできれば多少ごまかせるけど、結局それも他の部分との兼ね合いで「明るいところだったから暗くしたら、暗いところが暗すぎる」みたいになりがち。
・それはそれとしてスマブラforの終点の眩しいところは眩しすぎてザッケンナ! となった記憶はある(1:17のあたり)。まぁレタッチ監修の話ではないような気がしないでもないけど。
・ついでにsらに話を逸らすと、ベヨのステージとかファルコンのステージとかそうだけど、背景で動くものありまくるのメチャクチャめまいするし気が散るから、本当に背景はもっとシンプルに、動かすなら目立たないようにしてほしいんスよね……。
・マリオペイントのマウスカーソル芸細
・結局AIとかもそうだけど、他人の手を借りるだけだと完成度を高められないんだよなぁ、と思い知らされるやつ。「明確な完成図」が先で、出たものを「どう修正するか」というズレの修正がぼやけていると、一生ぼやけ続けるわけで。
・「頭の中に絵がある」という状況が、個人的には信じられない。多分僕は他人よりその能力が低いんだと思うけど、ぜんぜん頭に絵が出て来ないんだよなぁ。
モーションカテゴリの動画(G)
フォロースルーで印象が決まる 【モーション】

全部の格ゲーにこの動画の発生と終了のような見方ができるモーション確認モードがほしい
概要を説明したあとの「詳しくは攻撃モーションの内訳の回をごらんください」が、内部リンクの充実が完璧すぎて笑った。
なぜ桜井さんがこんなに説明がうまいかというと、前提として解説ジャンル分けが完璧 = 内容が完全に体系的になっている ということであり、関連することをすぐに引き出せる(ように動画を投稿している)から。本当に完璧。
後隙の設定が雑だと大味なゲームになるってのはなるほどでした。
この件がそもそも格ゲーの話かとは思うので若干趣旨ズレな気はするけども、マリオ(プラットフォーム2Dアクション)とかも「着地まで」をどうするか思考するのが楽しい説はある。
とは言えこの件に関しては桜井さんが本当に魂を込めたスマブラの一挙手一投足に関してなので、2Dインディーゲーレベルであれば知識として知ってれば十分で「ただ待機に補間するように戻す」で十分かとは思う。これは僕のあんまりゲームの見た目気にしない性格だからそう思うんかな? 変にモーションこだわってゲームとして不完全な作品を見るともっとこだわるところあるよね感が強い。
あとは個人的な好みとしては後隙短めゲームが好き。もちろん後隙が短いだけだと大味になると思うから、「予め予想して敵の攻撃を備える」という形式であることが前提だけども。
そういう点で言うなら、がんばりみのりことか本当に良かった。実質後隙とでもいいますか、攻撃の発生と後隙は短いんだけど、早めに回避行動(敵の攻撃の発生源から距離)を取っておかないとダメージという仕組みで「後隙設定」というゲーム側の責任よりは「自分の先読み回避能力の低さ」、「ダメージ稼ぎに欲張りすぎた」という自分の責任だと意識できるから不快感がなかった。
かなり話がそれた気がする。動画タイトル通り「フォロースルーで印象が決まる」はまさにその通りで、それです。(語彙力)
あとほんとにどうでもいいけど、アイクの横スマのところキャンセルできるという証明のためにジャンプボタンを連打しまくってるの理解ってちょっとフフッとなった。
モーション指定の仕方【モーション】
・桜井さんの余分な動きのないパンチすこ
・事前に「どういう動きになるか」という正解がすべて脳内にあるのがヤバイ。頭の中どうなってんだ?
・特にフレーム部分。どうなんだろう、モーションに携わり続けていたら「このくらいのフレームで動けばいいな」みたいなのわかるようになってくるんかなあ
・謎の間、草
・まぁ、ポーズ指定はこういうの使うのが一番よなぁ
・ガエンの前回避の「重い印象を高めるため、設置は長め」ってところ、そうなんだけど、「重い印象を高めたいから設置を長めにしよう」って最初から出てくるもんなんか? 僕(素人)なら見てから「設置長くしないとなぁ」みたいになるんだけども。
・マジでいきなりですが、ホムひかどの角度から何度みてもえっちすぎない? スマブラの風紀を乱すなよ!!!!!!!(もっとやれ
・1ファイターで70枚から80枚ということは、合計で7000枚近いポーズ指定してるってことだよなぁ。
・イカの原作のイカ感(表面のうっすらデコボコしてる感じとか)がすごい。スマブラは逆にトゥルンとしてちょっとおもちゃっぽくなってる感じ。
・手元に人形があるはずなのに自分の肩をグリグリする桜井さんお茶目
・どうして現実的でもない動きなのに「こうするのが良い」っとう完成形が頭にあるんだろうか。普段から妄想してるのかなぁ。「パックンフラワーは葉っぱを体の周りでぐるぐる回して飛ぶと面白い」みたいなw
エフェクトカテゴリの動画(H)
エフェクトをスローで見てみよう 【エフェクト】

「何を作るにしてもよく観察することが近道」ってのは本当に至言。
大事なことなのでもう一回書いとくけど「何を作るにしてもよく観察することが近道」って本当にそう思う。
意地の悪い言い方をするなら、ほとんどの解説って「見ない人」のための補助輪なんですよね。言い方を変えるなら「見ることさえできればだいたいのことはわかる」。
絵を模写する時の補助線として格子状のグリッド線を使うように、スローモーション(コマ送り)さえすればだいたいの「動き」に関することは分解できる = 分かるってことなので。
とは言え僕は別にモーションやエフェクトにあまり興味は無く真面目に見たことがなかったので、この動画にていくつか驚いたことを上げておくと……
- ファルコン下Bの上半身のひねってからのキックだったんか!
- ピカチュウ下Bのほっぺたの点滅があったんだ!
- ロゼチコの星を散らすエフェクトが花火みたいだなぁ
- クッパの横Bでつかんだ時対象を睨んで持ち上げる先を向く視線の動きが細かい!
- わざわざわかりやすいようにズームしてるけど、オリマーの頭のランプ? に残光? をつけることで光の動きがよりわかりやすくなるようになってるんだなぁ。
- ジャスガドンキー白目で草
- スティーブの素材採掘、ちゃんとつるはしが素材に引っ掛かるような「タメ」が入るのに驚いた。
という感じ。エフェクトというよりもモーションへの驚きが結構あったなぁ。ちなみにどうでもいいけどスターフォックスがBGM面で優遇されてるのはなんでだろうw
あと「エフェクトをバンバン出していきましょう」は桜井さんくらい「ゲームプレイにおける視認性」を意識している人なら良いと思うけど、下手な人にとっては諸刃の剣感はある。
サウンドカテゴリの動画(I)
音はフィクション、ノンフィクション 【サウンド】

なんやかんやでスマブラXの効果音が好きなスマブラ族は多いのでは?
・とは言えコメントにもあったけどマルスの先端の「ブリュ!!!」みたいな音はシリーズ随一の気持ちよさ。
・全然どうでもいいけどタイトルをみて恋はスリルショックサスペンスを思い出した(本当にどうでもいい)
・リアルな格闘技の映像を見て物足りないのはこれがある。
・逆に見る側として野球、やる側としてゴルフが好かれているのは、ヒット音が気持ちいからという個人的な仮説があったことを思い出した
・(その仮説もリズム天国をプレイしてからというゲーマーの顔)
・言うほど木や石を並べるリアルな音って聞いたことある? むしろなんかスナック菓子を食べる音とか、カロリーメイトを割る音とか、そういう気持ちよさのほうが近い気はする。
・「マイクラの音が気持ちいい」のは、割りと「リズム感が一定だから」ってのが大きい説を上げておく。
・以前足音の話がなんかの動画であったと思うけど、足音に関しては(ノイズチャンネルが有効に使えたという事情もあるけど)昔からリアル寄りだったような気はする。それによって臨場感がましていたような気もする。ドラクエの階段の「ザッザッザッ」しかり、スパルタンXのステージ開始時の「ザザザザザザ」しかり。
・ということを書いて思ったけど、「木の上を歩いた音」とか「石の上を歩いた音」とかがマイクラにおけるそれら素材を並べた音に近いのではと思えてきた。
・話は変わるけど、だからこそ「ビームの音」とか「バリアの音」とか、「無い音」を「なるほど、これがビームの音なんだな」と思えるような「創作」ができる人はすげぇよなぁ。
・映像もそうだけど「リアル」なのではなく「リアリティ」。「聞いた人がそうだと思える」ことが重要なんだよなぁ。
・全然関係ないけど、漫画とかでよく「おまえ……その傷……!」「え……?」みたいな感じで切られたことを気付いてないのあるしたまに現実の仰天エピソードみたいなやつでもあるけど、ヒットエフェクトとヒットストップとSEがなかったら自分が切られても気づけ無いってことありそうなくらい「手応え」に誇張がなければ感触が薄いってことだよなぁ
環境音楽としてのゲーム音楽 【サウンド】

「鳴っているか鳴っていないかわからなくて面白くない」は「直ちにファミコンのような音楽を鳴らせ」の意味ではないとは思うw
やっぱゲーム音楽はいいなぁ、などと思いました。
特に大好きなグラディウス2のBurning Heatが流れたときは思わず震えた。熱すぎる。
とは言え、やはり合っているかあってないかで言うとあってないものも多かったわけですが。
んでも、イー・アル・カンフーは特に違和感がありませんでした。
「視点」が原作と同じという要素が大きいのかな。格ゲー視点というか、真横に並んだキャラクターが殴り合うという要素。あとはGhost of Tsushimaも横に走る映像だったので脳がバグって「売上が芳しくなかった月風魔伝さん、また新作!?」となったり。
言い方を変えると、「T(F)PS視点」のゲーム(ファミコン時代にはほぼ存在しなかった視点のゲーム)は結構違和感ありますよねぇ。特にBattleFeald1なんかは違和感バリバリ。
んでも、それもまた視点の問題ではなく「FPSは環境音が多い」という経験からそう思ってしまっているのかも。同じ観点で言うなら「ゼルダの伝説のフィールド曲」が強烈に印象付けられているからブレスオブザワイルドのフィールドが物足りないと思うのかも。
余談ですが、Serious Samはそういった意味で戦闘音楽が主張するゲームっていうのも個人的には嬉しいポイント。
で、動画の話ですが、リアルにすると音の構成要素が増えすぎるから音楽を薄味にするって本末転倒感ありませんかね。
ゲーム(にかぎらずですが)って音楽がメチャクチャ重要じゃないですか? 「リアルな効果音」を優先すべきとはとても思えない。
多少不自然でもメチャクチャ熱い曲なら、その曲のチカラで「グアー、たまんねぇー!」となってゲームに対する評価も鰻登りじゃないでしょうか。というかだからこそ古のゲームたちは(今となってはクソゲーだとしても)もてはやされがちというか。それだけ音楽のチカラは偉大であり強大。
……そう思っているのは、老人ゲーマーのゲーム音楽信仰に依るものかなぁ。
んでもその理屈で東方やUndertaleのアレンジが山のように生まれVGMがそしてゲーム愛されている、さらに「アレンジ」という一つのムーブメントを巻き起こしているっていうような影響があることを考えると、やっぱりそれだけ「印象に残る音楽」は「ゲーム自体の感動」に大きく作用すると思うんだよねぇ。
あと「曲が多すぎるから覚えられない」というのも本当にそうかぁ? と思います。
HALOとかFalloutとかはそれこそ曲がメチャクチャ多いと思いますが、メインテーマがメチャクチャいい曲って記憶だけはあったりします。
でもメインテーマすら記憶にない。というかメインテーマ、あった? というかまともな音楽って1曲でもあった? とかそういうレベルのゲームありません?
それってもう「曲が多すぎる」とかそういう話じゃないと思うんだよなぁ。むしろそれなら曲を絞って1曲、1場面でも深く印象に残すところを作るべきだとすら思う。
で、「800曲以上」のスマブラスペシャルとかいうゲームがそういった点でも本当に偉大な作品だと思います。
「このスマブラ限定アレンジめちゃいいじゃん!」とか「スマブラのオリ曲たまんねぇ^~」ってなるので、やっぱり曲数ってあんまり関係なくていい曲かどうかってのが非常に大きな要素だと思うんですよね。
スマブラは格ゲー(何度も何度も繰り返し対戦する)なので、昔のゲーム同様繰り返し同じ曲を聞いて記憶に残りやすいという要素も込みですが、それにしてもです。
というわけで、僕はプレイヤーとしては「うるさい音楽が聴きたい」という気持ちが割りとあるんだなぁ。
余談ですが最近プレイしたゲームで東方を除くなら、フェノトピアのBGMがバリ良かったので、3Dゲームに合わないような音楽が聞きたい方は是非。
UI(J)
ローディング画面 【UI】

ちゃんとロードがロードしてる芸細すこ
ロード時間のロード感を薄くする例で言うと、(動画中にもある塊魂とかもそうだけど)PS2時代はなんらかの操作できるパターンがあったような気がしますね。
ドラゴンボールでサイバイマンを増やしまくった人も多いハズ。
コメントにあって驚いたのが「長いロードも最初の一回なら『映画館のいつ始まるのかなぁ』って雰囲気を味わえて好き」みたいなやつ。
めちゃくちゃ生きてるの楽しそうで非常に羨ましい。悪いところすら人生のワクワクに転換できるスキル? ポジティブシンキング? は本当に人間できてるなぁ、と思いました。
僕はロード時間にかぎらず「実質ロード時間」にすらキレているというのに……。
っていうか違うわ。リトライ前提ゲーにおけるリトライ時のロード含む、「繰り返すロード」を短くしろよって話だ。
コメント見てると、意外と開発者のロードに対する気遣いをしっかり味わった上で「なんならTIPS読みたいからもっと長くしろ」てきなのもあるわけで。個人的にもそこまで最近の作品で「リトライ部分」以外でロードの長さがきになることって無い気がする。それだけ世界観や攻略の補強としての「ロード画面」が一般的というわけで。非常によい傾向ですよね。まぁ、読みたいからロード終わるなとユーザーに思われてるのであれはそれはそれで調整不足だとは思いますが。
そして更に言うと、「なんならロード見せつけろ」ってところもあるかも。かなり個人的な意見かとは思うけども。
例えばバイオの例で言うと「ロードではなくドアを開けるモーション」だと思っていたら「ドア開けるのくらいレスポンスよくしろ」みたいなのあると思います。そこで逆にストレスためる説ない? ロードなら「Now Loading」にストレスはあるものの「とは言え仕方ない」と思えるけど、ドアを開けるという頻繁に発生するものの動作が遅いという頭で居たら「そこはなんでもっとレスポンスよくしなかったかなぁ」というマイナス点にすらなりそう。
話は変わりますし詳しくはないですが、今後ゲームのストリーミングが増えて通信速度も5Gやら6Gやらで爆速になったら、あんまりロードを意識することもなくなるんじゃ? とは思ってます。
もちろんそうなれないゲームもありますしそういう環境に適応しないゲームもたくさんあるので切って離せない問題だとは思いますが。んでも工夫次第でどうにかなるとは思うんですよねぇ。
結局ロード0が最高なので、基本ロード0ゲーが基準になるのはいつ頃なんでしょうね。
広報(L)
広報はかけ算【広報】

「知られなければないのと同じ」。身にしみますなぁ……
これほど大きな「広報」という車輪をまっすぐ進めるためのスマブラというゲームの「開発」がとてつもないというのがわかりますね。
仕事の質と量がマジでありえんのよなぁ、桜井さん。
(これは本当に自分にも言い聞かせたいんだけど)なんか「知られること(営業)」ってめちゃくちゃ嫌われる節がある。それに「黙って仕事の質を上げる」みたいなのかっこいいって空気あるけど、ほんと「知られなければないのと同じ」なんだよねぇ。
とは言えとは言え、金か手間あるいは両方がめちゃくちゃにかかるものだし、営業というとそれこそ永遠に最適解を探し続けなければならない分野のことでもあるからねぇ。他のカテゴリよりも深く広い知識が必要な非常に解説が難しい分野だと思うので今後の動画が楽しみな限り。
雑談(M)
マスターアップ【雑談】

ゲームづくりってみんなもう副業でやって飢える心配ない状態で作り込みたいだけ作り込んだ方が幸せじゃないですか?
結局マスターアップですっきり出来ないのって納期があるからで、納期は発売日を決めて広告を打つから発生するのであって、じゃあなんで広告しなきゃならないかというと売らなきゃならないわけで、なんで売らなきゃならないかというと売れないと社員を生活させることができなくなるからで。
極論ですが、仕事としてゲームを作ってるのが製作者の文句の出る諸悪の根源なんですよね。そりゃ昔は機材やらの関係で仕事としてじゃなきゃゲームづくりが難しいって側面も強かったかもしれませんが、今となってはそうじゃないでしょ。
別に無理やり仕事にして、不満を抱えたまま出さないほうが製作者にとっても幸福じゃないの?
個人で作るなら、別に気に入らなかったら無限にお蔵入りさせればいいだけだし。究極の(あるいは個人で妥協できる、後悔の無い範囲での完成形)ゲームを作って、出す。それでよくないですかね。
あとアプデの件も基本的にバグがあるからで、進行不能なんかの致命的な(昔もし発生したら回収レベルの)バグ以外は、もう、全部放置でいいんじゃないかなぁ、と僕は思ってます。
マジでたまにレビューで見るバグへの目くじら立てすぎ感、癌だと思ってます。
バランス調整アプデとかも、もう、各々でパラメーターイジれるシステムにすればいいだけでは?
あとDLCも、一つのタイトルから回収できる金を増やすという目的があると思いますが、結局それも一番最初の理論に則って「金を稼がなきゃならないから」で開発期間が伸びているわけで……。
と、まぁ、ゲームだけではなくゲームの開発にもそういう夢みたいなことばかりをついつい考えてしまいますね。
ゲームと目の疲れ 【雑談】

ゲーマー共通の困り事ですなぁ。
- 輝度下げる
- モニターから距離を離す
あたりはマジで大事ですねぇ。昔労働していたとき、輝度パキパキそこそこモニターが近くにならざるをえないような職場だったんですが、死ぬほど目がつかれてました。目がシパシパしてない瞬間がなかったレベル。
まぁ、環境云々はいろいろありますが、個人的には一番睡眠時間が大事だと思ってます。12時間くらい寝た日は目のシパシパを感じづらいです。
あと僕はブルーライトカットメガネをかけているんですが、効果があるかは謎。ブルーライトが睡眠の質に悪影響なんて話もありますが、ブルーライトカットメガネをかけても別に変わった感じもしないし目の疲れが軽減されている感もないですし。
と言ってもメガネを書けないとまともに目が見えない(視力0.02以下)ので、ブルーライトカットメガネが無い状態での目の疲労度との比較ができないため「疲れ目を感じまくってるけど、メガネを外したら実はもっとひどくなる」説はある。んだけど、どうなんだろうなぁ。
そもそもブルーライトカット率も色々あったりで正直「マイナスイオン」てきなものかと思ってるんですけど、どうなんですかね。
最近個人的には目の運動が効果がありまして、風呂に入っている間に28467391(格ゲーの入力方向)の順番でその方向を10秒ずつ思いっきり見詰めるというのを2セットやってます。終わった後スッキリするような気がしますし、実際風呂上がりは風呂に入る前にショボってた目がショボりづらくなっているような気がします。
んですがこれも結局風呂の湿気で目が潤っていたり、単純にモニターを見つめていない時間が休憩時間となっていたりとか、「その目の運動がダイレクトに効果発揮しているか」は謎なんだよなぁ。あとその目の運動をすることで風呂に入る時間が長くなり血行が良くなったのが原因であったり、とか。
んでもやってなかった時に比べると軽減されているという実感だけは少なくともあるので、やってます。
それとあずきのチカラとかそういう目を温めるやつも使ったことがありますが、単純に暖かくて気持ちい感じはしますがドライアイとかに効果があるかは謎です。逆に最近だと「働かせすぎた目をクールダウンするために冷やすほうが良い」というような内容も見たことがあるので、情報が錯綜しまくってます。
まぁ現在も試行錯誤中ということですね。
ゲームしながら運動のすすめ 【雑談】

ゲームする時間を「もったいない」と言うのがマジ桜井さん。
でも、わかる。僕も効率厨なので運動しなければならないと思ってるけど、運動時間がもったいないからどうするかを考えてステッパーを導入しました。かなり導入して正解だと思っていて、詳しくはレビューしたりもしてます。
桜井さんは「マルチタスクは生産性を落とす」という時代に真っ向勝負のエアロバイク&ゲーム&テレビというスタイル。まぁどれも「生産」ではないからいいのか? と思いつつ、ゲームとテレビは流石に音が混ざるだろと思ったり。
なので僕はやってもステッパー + ゲーム or Youtube or 読書 みたいな感じです。
あとたまーにステッパー + ゲーム + Youtubeみたいなのもやりますが、よっぽど気の抜けるゲーム(地球防衛軍の稼ぎとか)じゃない限りはゲームじゃ無い側のメディアの内容がほとんど入らないです。
なので、ゲーム音を消しても問題ないゲーム+ラジオ的な音声がメインのメディア、という組み合わせが限界ですねぇ。個人的には。それをこなせる桜井さんが本当に異能力。
と、いうわけで(?)健康を損なわないレベルで時間あたりに何をするか考えるの、楽しいですよね。これまさにゲームの好みと合致していて、「1ターンの濃度を高める」という体験、脳が喜びますよねぇ。
ちなみにちなみに、最近(という「最近」が10年以上前なのが老害ですが)WiiUくらいの世代からコントローラー無線化がデフォになっている気がして、運動しながらのゲームがはかどるようになってるんですよね。このまま電脳化して運動が不要になって脳波だけでキャラコンできるようになれば最高なんですけどねぇ!
ちなみにこの動画で出ているアイテムをまとめた記事も書いたりしました。
桜井さんと同じような環境を作りたいなと思っている方は是非見てみて下さい。
企画コンセプト(N)
メテオス 【企画コンセプト】

「爆弾で壊すというのはよくある。『溶ける、崩れる』などの表現の問題でもない」ってところ、本当に頷きすぎて首が折れた
これ、ほんとにメチャクチャ重要なところというか、「ゲームの面白さの生み出し方」として「そうあるべき」なところの本質だと思います。
「ゲームとしてそれは何をしているか」ってところへの洞察。
例えばなんですけど、僕がJRPGをつまらないと思う理由の一つに「やってることが延々と変わらない」ってのがあります。まぁ僕の考えるJRPGっていうのの7割はドラクエなのでドラクエで例えていきます。
例えば「メラミが使えるようになった」って、何か価値がありますか?
いや、もちろん、敵を倒しやすくなるというメリットはゲーム内に生まれます。
でもそれって「レベルを上げて攻撃力を上げて『たたかう』におけるダメージを伸ばす」のと本質的には違いがないんですよ。
そしてドラクエ含む多くのRPGは無限リソース(時間さえかければ延々とキャラクターのステータスやアイテム資産を増やせる)です。
つまり「メラミ」が使えようが、ゲームとしての戦略性はほぼ変わっていない。むしろ「メラミ」が使えない間に進むメリットがないので、「レベルを上げる」という退屈な行動が最適解になってしまうんですよねぇ。
「たたかう」と「メラ」の違いというのは戦略に繋がります。物理攻撃か、魔法攻撃か、という。「最適な行動を選ぶ」という選択肢が生まれる。ただそれも無限リソースが故に「弱点をつくという戦略性」の繰り返しによって「戦略性が失われる」んですよ。
「メラ」から「メラミ」になってもそれはダメージが変わるだけ。
そういう意味で「ヒャド」とか「バギ」とか、山のように呪文がありますが、やってることは何も変わりません。
アクション要素がない以上、「『弱点をつく』という体験」の繰り返しなんですよね。
「メラとかヒャドとか、色々呪文がある」ということがゲームとしての面白さにつながっていない。
本質は「レベルが上ってダメージが増えた」というだけなんですよ。
で、ゲームそのものにおいてもその傾向はよく見かけます。ナンバリングの新作が出るとかならず「こういう新しい技があるよ」みたいなのありますよね。んで「新しい技キター!」みたいに喜んでいる人がいるわけですよ。
それを見ると「(ゲームに対して)何も成長していない……」と安西先生みたいになります。
もちろんナンバリングにかぎらず開発中のゲームで「今回は新要素の発表!」みたいなのがあっても、それがまったく新しいゲームの面白さになっておらずただ「爆弾で壊す」ところから「溶ける、崩れる」になっているだけ、というのも本当によくあります。
だからこそ桜井さんの言う「爆弾で壊すというのはよくある。『溶ける、崩れる』などの表現の問題でもない」っていう話は「ゲーム性の本質」を掴みまくっている「さすが」としかいいようのない納得があります。
ちょっと話を戻すと、だからこそ有限リソースゲームでありランダム要素の多いシレンなどが好きなのかもしれません。
話がそれたので動画の話に戻します。
メテオス未プレイなのでやんないとなんですけど、この動画を見ている限りメテオスと比較するとぷよぷよのゲーム性ってちょっと不思議なんですよね。お邪魔ぷよの仕様(これは通とかSUNくらいまでをちょろっと触った程度しかやったことないので大きな間違いがあるかもしれませんが)って、「リターン」に繋がんないんですよ。
例えばパネポンみたいに「お邪魔を消したら自ブロックになって、反撃の手札になる」って仕様ならわかるんですよ。そこに駆け引きが生まれる。
でもお邪魔ぷよって消すだけでは反撃につながらないんですよね。消して、自分の導火線に火をつける、という2ステップが必要になる。さらに「消しいる間」「連鎖している間」は行動不能であり実質ターン制なので「相手の動きを一手止める(=おじゃまぷよ)」はイコール敗北なんですよね。
おじゃまぷよが降ってくるる→解決につながらない無意味な2手目を置く→敗北
という流れの「無意味な2手目を置く」の部分が、全く無意味。おじゃまが降ってきたあとのリスク・リターンが存在しない。有利な人が有利なまま終わる。
つまり、攻撃されたあとの「反撃」がめちゃくちゃ薄い。
そこも含めてぷよぷよとは如何にお邪魔を振らせないかというゲームだとは思うんですが、ゲーム性という面でいうなら「おじゃまぷよ」はあまり優れた駆け引きを生んでないと思います。
言い方を変えるなら「画面下からおじゃまが出てくる(テトリス方式)」とかなら導火線までを邪魔しない上、ぷよ落下開始から連鎖の始点に着火する反撃まで近くなるので理解できるんですが。
その点メテオスは「敵の攻撃をそのまま跳ね返せればそのままダメージ」という(見た目的にも)単純明快な仕様であることは非常に優れたゲームだと思います。
もちろんメテオを押し付け合うというゲームデザインもおもしろいなぁ、と。
とは言えそのあとの「キャラ差」に関してはよくもわるくもかなぁ、と思ったり。パズルゲームとしての操作と思考の練度を上げる以外にも対キャラ知識てきなものが要求されてぐっとハードルが高くなるような気はします。
ただ音楽や効果音が変わるというのは、どのゲームにも実装してほしい素晴らしい要素の一つですよね。
まとめなど
というわけで、「『桜井政博のゲーム作るには』を見て思うこと、感想」でした。
桜井さんのゲームチャンネル、いちゲーマーとして非常に興味深く様々なことを思いながら視聴しています。いや本当に。
で、ただ思ったり考えたりしているだけというのも勿体ない? と思ったので、感想やら思ったことをアウトプットしてみました。
常日頃から考えている興味深い「ゲームそのもの」について、非常に思考が刺激されるため思うことも言いたいこともたくさん出てきますよねぇ。
今後も追記予定です。
ぼやき
桜井さんのディレクション力、マジで常軌を逸してないか? そもそも論、「こういうゲームが完成形。こういうキャラクターモーション、サウンドが完成形」っていう明確な完成形がこれだけのボリュームのゲームに対して脳内にあるのが一番の特殊能力だと思うわ。
関連してそうな記事とか
僕が好きなゲームを100本くらい上げている記事です。
桜井さんが使っているエアロバイクやキーボードなどをまとめた記事です。

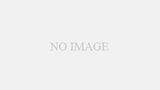
コメント(承認制のため反映まで時間がかかります)